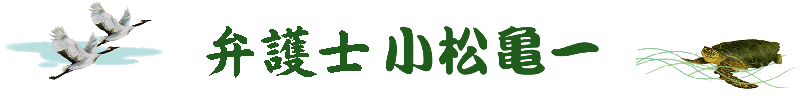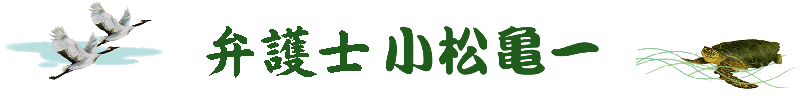○原告が、被告に対し、賃料1か月分の不払により賃貸借契約を解除したとして、その終了に基づき、賃貸した建物の明渡しを求めました。
○被告は、その1か月分の賃料等が滞納となっていることを本件訴訟が提起された後に初めて知り、これ以外の賃料等については、Cが原告に対して代位弁済していたので、原告と被告との間の信頼関係は破壊されていないから原告は本件賃貸借契約を解除することはできないと主張しました。
○これに対し、原告による解除の意思表示がされた時点において、被告が、原告に対し、同月分の賃料等の支払を怠っていたことは当事者間に争いがなく、一部の賃料等については、Cが原告に対して代位弁済していたものの、被告は、Cに対し、2万円を入金したのみであり、この時点で原告と被告との間の信頼関係が破壊されていなかったということはできず、原告の解除の意思表示により、本件賃貸借契約は解除されたものというべきであるとして、原告の請求を認容した令和6年12月4日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。
○被告は代位弁済したCに対し賃料代位弁済による求償債務合計71万8600円を支払っていますが、後の祭りで、この点は考慮されませんでした。
*********************************************
主 文
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、賃料不払により賃貸借契約を解除したとして、その終了に基づき、賃貸した建物の明渡しを求める事案である。
1 前提事実
(1)原告は、令和4年1月23日、被告との間で、賃貸借契約に基づき引渡していた別紙物件目録記載の建物を、次の約定で賃貸するとの更新合意をした(以下、この契約を「本件賃貸借契約」という。)(争いのない事実)。
ア 賃料等
賃料 月額13万円
共益費(管理費) 月額7000円
イ 支払条件等
被告は,原告に対し、毎月28日までに翌月分の前記アの賃料等を支払う。
ウ 契約期間
令和4年2月1日から令和6年1月31日まで
(2)
ア 原告は、令和6年3月8日、被告に対し、賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)1か月分の支払を怠っており、また、それに先立ち、賃料等約3か月分の支払を怠ったため、被告の委託を受けて原告に対して本件賃貸借契約に基づく被告の債務を連帯保証したC株式会社(以下「C」という。)が、原告に代位弁済をしたとして、3日以内に賃料等1か月分を支払うよう催告するとともに、これを支払わなかった場合には、本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をした(争いのない事実、甲3、乙3)。
イ 前記アの当時、被告は、原告に対し、令和5年12月分から令和6年3月分までの賃料等の合計54万8000円の支払をしていなかったため、Cが、原告に対し、このうち3か月分の41万1000円を代位弁済していたところ、被告は、Cに対し、2万円支払ったのみであった(甲5)。
(3)被告は、Cから求償権について催告を受け、令和6年4月19日、Cに対し、以下の合計71万8600円を支払った(争いのない事実)。
保証委託料 1万円
保証事務手数料 1万1880円
令和5年12月分 11万9970円
令和6年1月分 13万7000円
令和6年2月分 13万7000円
令和6年2月分 16万5750円
令和6年4月分 13万7000円
2 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は、原告による本件賃貸借契約の解除の可否であり、これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(被告の主張)
原告による解除の意思表示がされた令和6年3月8日時点において、同月分の賃料等が滞納となっており、原告がCに対してした同年4月19日の入金や、その後の入金によっても、同年3月分の賃料等が滞納のままであることは認めるが、被告は、同年3月分の賃料等が滞納となっていることを本件訴訟が提起された後に初めて知った。そして、これ以外の賃料等については、Cが原告に対して代位弁済していたことからすれば、原告と被告との間の信頼関係は破壊されていないのであって、原告は、本件賃貸借契約を解除することはできない。
(原告の主張)
原告が被告に対して解除の意思表示をした時点で、被告には令和6年3月分の賃料等の滞納があったし、原告は、被告に対し、予備的に令和6年5月2日に送達された訴状をもって、支払期限の経過した賃料等を3日以内に支払うよう催告し、支払がなければ本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をしたから、本件賃貸借契約は解除された。
また、前提事実(2)の原告による解除の意思表示の時点において、原告は、被告に対して令和6年3月分の賃料等の支払を怠っていたのみならず、令和5年12月分の一部並びに令和6年1月分及び同年2月分の賃料等につき、代位弁済したCに入金していなかった。Cが原告に代位弁済したとしても、被告による賃料等の不払いという事実は変わらないのであり、以上のCに対する滞納状況等にも鑑みれば、上記解除の意思表示の時点において、原告と被告との間の信頼関係は破壊されていたというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 前提事実(2)のとおり原告による解除の意思表示がされた令和6年3月8日時点において、被告が、原告に対し、同月分の賃料等の支払を怠っていたことは当事者間に争いがなく、前提事実(2)のとおり、令和5年12月分から令和6年2月分の賃料等については、Cが原告に対して代位弁済していたものの、被告は、Cに対し、2万円を入金したのみであった。
そして、前提事実(2)によれば、原告は、令和6年3月8日、被告に対し、3日以内に滞納していた賃料等を支払うよう催告し、その支払がないときには解除するとの意思表示をしたのであって、その催告期間内に被告が賃料等を支払ったとは認められないところ、被告は、Cがした41万1000円の代位弁済に関し、Cに対して一部である2万円を支払ったのみで全額の支払をしていなかったというのであるから、この時点で原告と被告との間の信頼関係が破壊されていなかったということはできず、上記解除の意思表示により、本件賃貸借契約は解除されたものというべきである。
2 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第7部 裁判官 荒谷謙介
別紙 物件目録
1 所在 世田谷区α×丁目 ××番地×
家屋番号 ××番×の×
種類 共同住宅
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
床面積 1階 107.86平方メートル
2階 110.23平方メートル
3階 86.08平方メートル
4階 63.36平方メートル
上記建物のうち2階×××号室40.64平方メートル部分
以上
以上:2,855文字
|