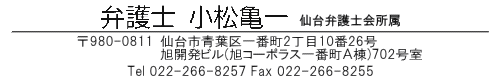| 旧TOP : ホーム > 交通事故 > 交通事故判例-脊椎脊髄関係症等 > | |
| 旧TOP : ホーム > 交通事故 > 交通事故判例-脊椎脊髄関係症等 > | |
| 令和 1年 7月17日(水):初稿 |
|
○外傷後の頚髄症と交通事故との因果関係を認めた判例を探していますが、交通事故により頭部外傷I型、腰部側胸部打撲症、外傷性頚髄症の傷害を受け、頚髄症に基づく後遺障害(8級該当)を残した被害者(50歳・女)につき、事故後の症状に同人の自律神経失調症、高血圧症、肩甲関節周囲炎等の既応症と加齢による頸椎の退行性変化に事故による外力が加わって症状の増悪、拡大をもたらしたものであるとして、外傷性頚髄症と事故との間の相当因果関係が認められた平成6年11月24日神戸地裁判決(交民27巻6号1711頁)の関連部分を紹介します。 ○同判決は、交通事故の被害者が罹患していた疾患が損害の発生ないし拡大に寄与した場合、損害額の算定に当たり、損害の公平な分担の見地から、民法722条2項の規定を類推適用してこれを斟酌することができると解すべきで、被害者の事故後の症状については、事故前から既往症や加齢による頚椎の退行性変化が大きく寄与していることは明らかであり、その寄与の程度は少なくとも3分の1の割合を下回ることはなく、損害額の算定に当たっては、その全額について3分の1を減額するのが相当しました。 ********************************************** 主 文 一 被告らは、原告に対し、各自、金129万5980円及びこれに対する平成元年4月13日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 三 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の、その余を被告らの各負担とする。 四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 原告の請求 被告らは、原告に対し、各自、金1351万5465円及びこれに対する平成元年4月13日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。 第二 事案の概要 一 本件は、被告京都タクシー株式会社(以下「被告会社」という)の従業員である被告森田進(以下「被告森田」という)運転のタクシーの乗客であつた原告が、右タクシーと被告内藤喜一(以下「被告内藤」という)運転の普通乗用自動車が衝突して発生した交通事故によつて損害を被つたとして、被告ら全員に対し損害賠償を請求した事案である。 (中略) 第三 争点に対する判断 一 本件事故と原告の症状との間の因果関係の有無 1 原告の本件事故前後における症状等について まず、前記「争いのない事実など」の項で判示した各事実と証拠(甲1ないし9号証、14号証、15号証の1ないし3、乙1、2、10号証、16号証の1ないし10、17、18号証、19号証の1ないし3、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の各事実が認められる。 (一) 原告(昭和14年6月26日生)は、本件事故(平成元年4月13日発生。満47歳)当時、殆ど就労しておらず、昭和56年頃以降、独り暮らしのため、生活保護を受給して生活していた(なお、原告には、昭和46年頃、るいれき[結核性頸部リンパ節炎]の既往症があつた。)。 (二) 原告は、昭和58年12月13日以降本件事故時までの間、自宅近くの旭診療所に頻繁(ほぼ2日に一回の割合)に通院し、自律神経失調症、高血圧症及び気管支炎(さらに平成元年2月以降は肩甲関節周囲炎等が追加)の診断名によつて治療を受けており、その間、頭痛、めまい、動悸、異常発汗、関節痛、四肢の痙攣・知覚異常、握力低下、膝蓋腱反射の亢進等多様な症状を訴えていたが(なお、主治医は、ギヤランバレー症候群[感染性の神経炎]の疑いを持つていた。)、昭和63年1月頃以降(一時期の再発を除いて)、右症状のうち動悸、冷感及び四肢の痙攣等については症状の軽減がみられるようになつた。 (三) (1) 原告は、本件事故によつて、頸部から右肩の痛みと腰痛等を訴え、同事故直後、同事故現場近くの市立舞鶴市民病院において治療を受け、前記のとおり「頭部外傷Ⅰ型、腰部側胸部打撲傷、外傷性頸髄症」と診断された。 (2) 原告は、右診療時において、同病院担当医に対し、以前から右足の脱力感があつたことを説明したが、担当医においては、レントゲン検査上第3―第4頸椎の強い不安定性、頸椎の多椎間ヘルニア(ただし、本件事故による受傷前のものと診断)や脊椎管狭窄を認め、また、右上肢の知覚過敏、膝蓋腱反射やホフマン反射、バビンスキー反射(手足の指等の反射)等について異常を認めた。 (四) 原告は、平成元年4月18日、右病院から神戸市中央区内の川北病院に転医し、同年5月3日までの間前記のとおり入通院して投薬や理学療法等による治療を受けたが、その間、頭痛、頸部痛、悪心、めまい、吐気、不眠、右半身の疼痛と脱力感、坐骨神経痛等多様な症状を訴えた。 (五) その後、原告は、右症状の軽減がみられないため、同年5月12日からさらに神戸海岸病院に転医し、膝蓋腱反射やホフマン反射、バビンスキー反射及びトロンマー反射等について異常が認められたため、同月15日に入院し、CTスキヤン検査等による精査の結果、脊髄症が原告の症状発現の原因であると診断され、「頸椎後縦靱帯骨化症」と併せて「外傷後頸椎症性脊髄症」と診断された(甲5、8号証の各診断書と乙19号証の2の14枚目及び15枚目の各診断書[平成元年9月10日付]参照)後、同年6月21日、第2頸椎から第7頸椎にかけて頸部脊柱管拡大術を受け、その後は入通院しながら同病院においてリハビリ治療を受けた。 (六) しかしながら、原告の前記各症状は、その後も改善されず、その結果、平成2年2月21日、右病院において、頚部から頭部にかけての痛み、四肢の痙攣・痛み・知覚異常、腱反射異常、上肢の挙上制限、歩行障害、さらに頚椎(脊柱)の障害、頚椎の可動域制限等の後遺障害を残したまま症状が固定した旨の診断を受けた。 (七) なお、原告は、本件事故後、以上のとおり入通院による治療を受けていた期間中においても、平成3年2月頃に至るまでの間、右治療と併行して前記旭診療所に通院し、前記高血圧症、肩甲関節周囲炎や高脂血症等について治療を受けた。 2 本件事故と原告の本件事故後の症状との間の因果関係について (一) ところで、被告会社及び被告森田において、原告の本件事故後の症状のすべてが既往症である自律神経失調症や高血圧症、頚椎の退行性変化等に基づいて同事故前から既に生じていた症状と同一であるなどとして、同事故と同事故後の症状との間の因果関係を争つていることは前記のとおりである。 (二) そこで、検討するに、前記1で認定した事実関係によると、原告は、本件事故前の昭和58年12月頃以降、自律神経失調症、高血圧症や肩甲関節周囲炎等のために長期間にわたつて治療を継続し、その間、頭痛、めまい、動悸、異常発汗、関節痛、四肢の痙攣・知覚異常、握力低下、膝蓋腱反射の亢進等自律神経系及び運動神経系に関する多様な症状を訴えていたが、昭和63年1月頃以降には、右症状のうち動悸、冷感や四肢の痙攣等についてはいつたんある程度改善されたにもかかわらず、本件事故後に再びかなり悪化していること、また、原告の右多様な症状のうちでも、本件事故後に至つては、手足の指等に関する反射異常が顕著になり、また、頚椎の可動域制限等が生じていることが認められる。 さらに、本件事故前後における右症状の変化に関する事実に証拠(証人西岡淳一の証言及び同人による本件鑑定)を総合して考えると、原告の本件事故後にみられる右のような症状の変化については、同事故によつて頚部に加わつた外力に基づいて、従前から存した症状がさらに増悪、拡大したことによるものであることを認め得ないではないというべきである。 (三) そうすると、原告の本件事故後に生じた前記症状の増悪、拡大と同事故との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 それゆえ、また、原告が右症状の治療のために受けた頚部脊柱管拡大術については、同事故後の症状改善のために必要な手術であつたというべきである。 以上の認定判断に反する被告会社及び被告森田の前記主張は採用できない。 3 原告の既往症等の寄与 (一) 次に、被告会社及び被告森田は、本件事故が原告の同事故後の症状に与えた影響の割合は極めて小さく、同事故前からの既往症等が大きく寄与している旨主張する。 (二) そこで、検討するに、交通事故の被害者が罹患していた疾患が損害の発生ないし拡大に寄与した場合、損害額の算定に当たり、損害の公平な分担の見地から、民法722条2項の規定を類推適用してこれを斟酌することができると解すべきである(最高裁判所第一小法廷平成4年6月25日判決[民集46巻4号400頁]参照)。 そして、これを本件についてみると、前記1で認定した事実関係によると、原告については、本件事故前から、自律神経失調症、高血圧症や肩甲関節周囲炎等のために多様な症状を訴え、長期間にわたつて通院治療を受けており、右症状はかなり難治化していたこと、そして、原告の本件事故後の症状と同事故前の症状の対比においては、かなりの部分が重なり合うものであることが認められる。 さらに、原告の頚椎に関するレントゲン検査上の所見についても、本件事故直後の市立舞鶴市民病院においては、頚椎の多椎間ヘルニアについては本件事故による受傷前のものとする旨の診断がされていたり、その後の神戸海岸病院においても、頚椎後縦靱帯骨化症との診断がされていたことは前記認定のとおりであり、また、証拠(前記西岡証人の証言と本件鑑定)によると、西岡鑑定人は、右レントゲン所見につき、原告の頚椎には加齢による変化の像(第2頚椎から第7頚椎にかけての椎体変性及び椎間狭少化、アライメントの異常)が認められるとして、変形性脊椎症による脊髄の圧迫が存在していた旨判定していることが認められる。 以上の事実によると、原告の本件事故後の症状については、同事故前からの前記既往症や加齢による頚椎の退行性変化が大きく寄与していることは明らかであるといわなければならない。したがつて、これに反する原告の主張は採用できない。 そして、これまでの全認定説示を総合して考えると、右寄与の程度は少なくとも3分の1の割合を下回ることはないというべきである。 (三) よつて、原告の後記損害額の算定に当たつては、その全額について3分の1を減額するのが相当である。 以上:4,290文字
|