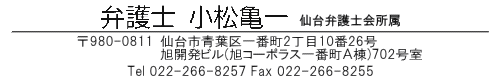| 旧TOP : ホーム > 法律その他 > 使用者・労働者 > | |
| 令和 5年 5月 9日(火):初稿 |
|
○○「中小企業退職金共済退職金と就業規則退職金規程を判断した地裁判決紹介2」で「被共済者が退職金を受給する権利を保護する中退法の各規定は,これに反する私法上の合意の効力を認めない強行法規であると解するのが相当」との判断をした平成25年8月30日東京地裁判決(ウエストロージャパン)関連部分を紹介していました。 ○中小企業の退職金積立については、中小企業退職金共済の外に、商工会議所が実施している特定退職金共済制度があります。この特定退職金共済制度による退職金の帰属について、これは退職金の原資を保全するためのものではなく、退職金の支払そのものを確保するためのものであり、退職金の請求権は、制度に加入している企業ではなく、直接退職者に帰属するとして、倒産した企業の従業員から商工会議所に対してなされた退職金支払請求が認容された平成10年11月4日甲府地裁判決(労判755号20頁)関連部分を紹介します。 ○判決では、掛金と加入期間に応じて計算される退職給付金は、特定退職金共済団体から直接従業員に支給されるため、退職一時金の額が事業主の退職金規程による退職金額を上回る場合であっても、また、退職金規程において自己都合、会社都合等の退職事由により支給額に差が設けられていたとしても、さらに、勤続年数が短い者に対しては退職金を支給しないとの定めがあったとしても、特定退職金共済による退職一時金の支給額には影響を及ぼさないとして中退金退職金と同様に判断しています。 ********************************************** 主 文 一 被告は、原告らに対し、それぞれ別紙原告一覧表の「特定退職金共済制度一時金」欄記載の金員及びこれに対する平成9年3月4日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 三 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 請求 主文同旨(平成9年3月4日は被告に対する訴状送達の日の翌日である。) 第二 事案の概要 本件は、原告らが被告に対し、いわゆる特定退職金共済制度に基づく退職一時金の支払を求めた事件である。 一 争いのない事実等 1 原告らはいずれも、株式会社A(以下単に「A」という。)の元従業員であり、それぞれの入社及び退職の日は別紙原告一覧表〈略〉の「雇入日」欄及び「退職日」欄に各記載のとおりである。 2 被告は、所得税法施行令73条一項の特定退職金共済団体として、税務署長の承認を受け、退職金共済事業を実施している社団法人である。 3 Aは、被告と間(ママ)で、退職金共済契約(Aが被告に掛金を納付し、被告がAの従業員の退職について退職給付金を支給することを約する契約)を締結していた。 4 原告らがAを退職したことに伴い、被告が右退職金共済契約に基づいて支給すべき退職給付金の金額は、それぞれ別紙原告一覧表の「特定退職金共済制度一時金」欄記載のとおりである。 5 被告は、原告らの退職について支給すべき右退職給付金をいずれもAに支払った。 二 争点 (中略) 第三 争点に対する判断 一 証拠(〈証拠・人証略〉、原告輿水)及び弁論の全趣旨によれば、次のような事実が認められる。 1 特定退職金共済制度は、事業主が共済契約者、その従業員が被共済者となり、事業主が所得税法施行令73条に定める特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結して掛金を納入することによって、その従業員が退職したとき又は契約が解除されたときに、その掛金と加入期間に応じて計算される退職給付金(退職のときは退職一時金、解除のときは解約手当金であるが、以下では単に「退職一時金」という。)が従業員に対して支給される制度である。 2 この制度は、従業員の退職金を確保するためのもので、退職一時金の受取人は被共済者である従業員に限られ、事業主が受取人となることはできないものとされており、事業主がこの制度を採用した場合には、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済制度(以下「中退金」という。)を採用した場合と同様に、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)5条による退職手当の保全措置を講じたものと取り扱われる。 3 事業主は掛金の全額を負担しなければならず、また、掛金として払い込まれた金額を事業主に返還することはできないものとされているが、その反面、事業主が負担した掛金は全額損金に算入することができ、従業員の所得税の対象にもならない等の税法上の特典が認められている。 4 退職金制度を有する事業主が特定退職金共済を採用する場合には、既存の退職金制度とは別個の制度として特定退職金共済を採用し、両者を別枠でそれぞれ支払う方法(併給制)を選択することもできるし、特定退職金共済による退職一時金を既存の退職金制度による支給額の内払とみなして、差額だけを事業主が従業員に直接支払う方法(内枠支給制)を選択することもできる。 5 事業主が右4のいずれの方法を選択した場合でも、退職一時金は特定退職金共済団体から直接従業員に支給されるため、例えば、退職一時金の額が事業主の退職金規程による退職金額を上回る場合であっても、また、退職金規程において自己都合、会社都合等の退職事由により支給額に差が設けられていたとしても、さらに、勤続年数が短い者に対しては退職金を支給しないとの定めがあったとしても、特定退職金共済による退職一時金の支給額には影響を及ぼさない。 6 したがって、右のような退職金規程の内容を特定退職金共済による退職一時金の金額に反映させるためには、事業主において、退職金規程を満たす勤続年数が経過した後に特定退職金共済に加入するなど、掛金額や加入時期を調整する必要がある。また、懲戒解雇などによって退職した従業員に対する支給額を減額するには、事業主が特定退職金共済団体にその旨を申し出て、退職金共済審査会の議を経なければならないものとされている。 7 支給手続は、被共済者である従業員が退職したときに共済契約者である事業主が特定退職金共済団体に届け出るとともに、従業員は事業主を通じて退職一時金を請求するものとされている。なお、中退金の制度趣旨や仕組みも、基本的には特定退職金共済のものと変わらないが、支給手続については、契約成立時に中小企業退職金共済事業団から従業員に対して退職金共済手帳が交付され、従業員が退職した場合には、この手帳に基づいて従業員本人が右事業団に退職金を請求することになっている。 8 被告は、現在では退職一時金を退職者に直接支払っているものの、平成8年に本件の紛争が生じたころまでは退職一時金を事業主経由で退職者に支払っており、このような支給方法によって問題が生じたことはなかった。原告らに対する退職一時金についても、従前と同様の方法で、事業主であるAから原告ら(一部の原告らを除く。)の委任状が添付された退職通知書兼一時金請求書(又は解約通知書兼解約手当金請求書)と、Aの口座を振込先に指定した給付金(又は脱退一時金)送金方法指定書が提出されたのを受けて、Aに支払ったものである。 9 Aは、特定退職金共済だけでなく、中退金にも重複して加入していたが、前者についての被告の運用が右8のとおりであったため、Aの代表者は、中退金による給付金は直接従業員に支払われてしまうのに対し、特定退職金共済による給付金はいったんは被告からAに支払われ、Aが従業員に支払うことになるので、Aが従業員に対して支払うべき退職金の原資になると認識しており、Aの退職金規程に従って従業員への支給額を決定することができ、残額が出ればAの雑収入に計上することができると考えていた。 10 Aには退職金規程があり、これによれば退職時の勤続年数及び退職事由別に支給額を決定するものとされているが、特定退職金共済及び中退金による給付金との関係については全く触れられておらず、原告らを含む大半の従業員はAが特定退職金共済を採用していることを知らなかった。 11 Aの退職金規程には、退職引当金を従業員と会社が2分の1ずつ負担し、従業員の負担分は毎月の給料から控除するものとされており、この給料からの控除分は退職積立金として退職時に返還する扱いであったところ、原告らの一部が右積立金の返還を受けていないと主張したため、平成8年6月ごろから、原告らの代表者と労働基準監督署の担当者やAの代表者、被告の担当者との間で交渉が行われた。 この交渉の過程で、Aが被告との間で締結していた退職金共済契約による退職一時金が被告からAに対して既に支払済みであることが明らかとなり、原告らが主張していた退職積立金の金額とAが被告から受領した退職一時金の金額とが近かったことから、最終的には同年8月ごろ、穏便な解決を図るため、Aが被告から受領した退職一時金に相当する金額を原告らに支払うこととされた。しかし、Aは、この合意に基づく支払を履行しないまま、事実上倒産してしまった。 二 右認定の事実によれば、特定退職金共済制度は、退職金の原資を保全するためのものではなく、退職金の支払そのものを確保するためのものであり、退職一時金の請求権は直接に退職者に帰属し(ただ事業主を通して請求するものとされているにすぎない。)、その支給額は原則として掛金と加入期間とに応じて一律に決まるものであって、事業主の退職金規程の内容やこれに基づく支給額によっては左右されない(逆に、事業主において、退職一時金が支給された場合にこれを退職金規程に基づく支給額の内払とみなすことはできる。)と認めるのが相当である。 三 そこで、右のような特定退職金共済の性格を前提に、被告の主張(抗弁)について検討する。 1 退職一時金の支給について代理受領が認められるか否かはさておき、本件において、被告が原告らに対する退職一時金をAに支払うこと(Aが退職一時金を代理受領すること)について原告らが明示的に承諾をしたと認めるに足りる証拠はない。退職一時金の受取をAに委任する旨の原告ら名義の委任状が存在し、この点について(人証略)は、原告らはAが被告から退職一時金を受領することを承知していたと証言するが、右証言は他の証拠に照らして採用することができず、他に右委任状が原告らの意思に基づいて作成されたと認めるに足りる証拠はない。 また、Aの退職金規程には退職金支給のために退職金共済契約を締結する等の定めはなく、大半の従業員らはAが特定退職金共済を採用していることを知らなかったというのであるから、たとえ従前から被告が退職一時金を事業主であるA経由で退職者に支払っていたとしても、このような支給方法について原告らが黙示的包括的な承諾をA及び被告に与えていたとみることもできず、他に原告らの承諾を認めるに足りる証拠はない。 被告は、従前は事業主経由で退職者に退職一時金を支給するのが通常であったし、それで問題もなかったと主張するが、このような事業主経由の支給方法は先に認定した特定退職金共済制度本来の姿にもとるといわざるを得ず、ただ従前は事業主経由で退職者に支給する方法が内包する問題が顕在化しなかったにすぎないから、Aに対する支払が従来から行われてきた方法であるからといって、被告のAに対する支払をもって原告らに対する有効な弁済とみることはできない。 以上の点を実質的に考えてみても、本件は、被告が退職一時金を原告らに直接支給しないで事業主であるAに支払ったところ、Aが倒産してしまい、Aから原告らには退職一時金が支払われなかったというもので、いわばAの倒産によって生じた不利益を原告らと被告のいずれが負担すべきかの問題ととらえることができるが、この不利益は、制度本来の姿にもとる支給方法をとっていた被告が負担すべきであり、何らの落ち度のない原告らにその負担を強いる理由は見いだせないといわざるを得ない。 したがって、原告ら請求の退職一時金は弁済済みであるとの被告の主張(前記第二の二1)は採用することができない。 2 次に、前記認定のとおり、平成8年8月ごろに原告らの代表者とAの代表者、被告の担当者との話合いの結果、Aが退職一時金相当額を原告らに支払うとの合意が成立したことが認められるが、この合意は、原告らにとって、退職一時金相当額の支払を受けることができるのであれば、支払をするのが被告かAかにこだわる理由はなく、被告からAに対して退職一時金が支払済みであることをも踏まえて、Aから支払の約束を取り付けたにとどまるものとみるのが相当であり、それ以上に制度本来の姿にもとる被告の支給方法を追認したとか、被告の支払義務を免除したなどと解することは到底できない。 したがって、被告の退職一時金支払義務については原告らと被告及びAとの話合いによって解決済みであるとの被告の主張(前記第二の二2)も採用することができない。 3 第三に、Aの退職金規程による支給額との関係であるが、先に認定したとおり、Aの退職金規程の内容及びこれに基づく支給額は、原告らの被告に対する退職一時金請求権の存否を左右するものではないから、Aの退職金規程による原告らの退職金額がいくらになるか、またそれが実際に支払われたかどうかについて判断するまでもなく、Aの退職金規程による退職金額が特定退職金共済による支給額を制限するとの被告の主張(前記第二の二3)は採用することができない。 四 以上によれば、原告らの請求はすべて理由がある。 (裁判官 萩本修) 以上:5,567文字
|