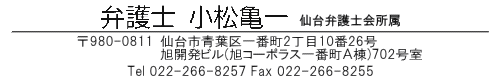| 旧TOP : ホーム > 男女問題 > 財産分与・慰謝料 > | |
| 令和 2年 7月30日(木):初稿 |
|
○「標準を上回る婚姻費用支払分の財産分与前渡を否認した高裁決定紹介」の続きで、清算的財産分与において過去の婚姻費用の分担の態様を斟酌してその額,方法を定めうるとした昭和53年11月14日最高裁判決(判タ375号77頁)の原審(控訴審)である昭和53年2月27日東京高裁判決(最高裁判所民事判例集32巻8号1542頁)を紹介します。 ○事案は、1審原告妻(反訴被告)が1審被告夫(反訴原告)に対し、離婚とともに財産分与(1審の600万円から2000万円へ請求拡張)の支払、2人の女児(13歳、7歳)の親権者を原告に指定すること、及び慰謝料1000万円の支払を求めめたものです。 ○東京高裁は、婚姻の主な破綻原因は被告にあり、原告が実家に戻ったことは悪意の遺棄とは認められないとして民法770条1項5号に基づく離婚を認め、子らの親権者を原告とした上で、財産分与として、離婚後の生活扶助金600万円及び過去の生活費等400万円の合計1000万円の支払、さらに、慰謝料として、被告の責任の程度、双方の社会的地位などを総合考慮して300万円の支払を命じました。 ○判決は、「3の過去の生活費、教育費の清算相当額として金400万円(かかる費用は婚姻費用であるから、それ自体としては、過去の分についても家庭裁判所が分担を決定すべきであるが、財産分与額決定に際しての事情の一つとして、右費用支弁の清算を考慮に入れることは相当である」としています。 **************************************** 主 文 一 一審原告(編者注ー第2265号離婚等請求事件被控訴人、第2309号離婚等請求反訴事件控訴人ー以下同じ。)の控訴及び請求の拡張に基づき、原判決中一審原告の金員請求に関する部分(原判決主文第三項及び第四項)を次のとおり変更する。 1 一審被告(編者注ー第2265号離婚等請求事件控訴人、第2309号離婚等請求反訴事件被控訴人ー以下同じ。)は一審原告に対し、1300万円を支払え。 2 一審原告のその余の請求を棄却する。 二 1 一審被告の控訴に基づき、原判決中一審被告の反訴請求を棄却した部分(原判決主文第5項)を取消す。 反訴請求に基づき、一審被告と一審原告とを離婚する。 2 一審被告のその余の控訴を棄却する。 三 本訴及び反訴の訴訟費用は、第1、2審を通じ、その3分の1を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。 四 この判決は、第一項1のうち、金300万円にかぎり、仮に執行することができる。 事 実 一審被告は、一審被告の控訴(第2265号事件)につき、「原判決中一審被告敗訴の部分を取消す。一審原告の本訴請求をいずれも棄却する。(反訴につき)一審被告と一審原告とを離婚する。一審被告と一審原告との間の長女貞子及び二女貴子の親権者をいずれも一審被告と定める。本訴及び反訴の訴訟費用は、第1、2審とも一審原告の負担とする。」との判決を求め、一審原告の控訴(第2309号事件)につき、その棄却の判決を求め、さらに、一審原告の当審における拡張請求につき、本案前の答弁として「一審原告の請求を却下する。」との判決、本案の答弁として「一審原告の請求を棄却する。」との判決を求めた。 一審原告は、一審被告の控訴につき、その棄却の判決を求め、一審原告の控訴につき、「原判決中一審原告敗訴の部分を取消す。一審被告は一審原告に対し、さらに金2200万円(うち当初の請求金800万円、当審における拡張請求金1400万円)を支払え。本訴及び反訴の訴訟費用は、第1、2審とも一審被告の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求めた。 当事者双方の主張は、以下に訂正、付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 (一審原告の主張) 一 原判決9丁表2行目の「生活費等」を「生活費、教育関係費」と改める。 二 同9丁裏3行目の「金600万円」を「、前記一審被告の土地の共有持分の時価の4分の1以下である1000万円と、前記一審原告が支出した二児を含めての生活費、教育関係費1000万円(かかる費用は、婚姻費用として、財産分与額決定にあたり、「一切の事情」に含めて考慮されるべきである。)とを考慮し、金2、000万円(当初の請求金600万円を拡張する。)」と改める。 三 右生活費、教育関係費の年度別内訳は別表のとおりであるが、その合計額1428万3032円から、一審原告の昭和49、50、51年の収入合計156万3302円を控除した1271万9730円が一審被告の分担すべき額であるが、そのうち1000万円を主張するものである。 (一審被告の主張) 一 一審原告は、原審において財産分与として金600万円を請求し、その全額が認容されているのであるから、この点について控訴の利益を欠き,当審で拡張した金1400万円の財産分与請求は不適法である。よつて、第一次にその却下を求める。 二 本案の答弁として、一審原告がその主張のように二児を含めての生活費、教育関係費を支出したことは不知。 理 由 第一 一審原被告の経歴、婚姻、長女貞子、二女貴子の出生の各事実、婚姻関係の推移と別居その他本件係争に関する一切の事情、及び一審原被告の資産関係等についての当裁判所の認定は、以下に訂正、付加するほか、原判決理由第一項(原判決18丁表2行目から27丁裏4行目まで)と同一であるから、これを引用する。 一 原判決19丁表冒頭に「同第18号証、」を、同2行目から3行目にかけての「藤野暉、」の次に「同千葉翠、同小山龍次、」を挿入し、同3行目の「第一ないし第三回」を「原審第一ないし第三回及び当審」と、「第一、第二回、」を「原審第一、第二回及び当審。」と改める。 二 同20丁裏6行目の「被告は、」から同10行目末尾までを「被告は、前記のようなつき合い重視の生活をする一方で、家庭内においては原告に対し、お前は苦労を知らないから苦労させるのだなどと言つて、毎月被告から原告に渡す金員(当初は1万円程度)できりつめた生活をさせ、原告の学院からの給与も原告に渡さず、被告がこれを管理していた。」と改める。 三 同21丁表1行目から2行目にかけての「その日常生活の不節制はますますひどくなるばかりで、」を「その日常生活は、原告にとつては、およそ教師らしからぬ、節度と品格を欠いたものと思われたので、」と改め、同4行目の「昭和40年ころ、」から同7行目末尾の「釈然としないまま、」までを削り、同個所に「また、原告は、被告の性関係が乱れているのではないかと疑いをもつたこともあつたが、明確な証拠もないので(後記(八)の事実は、本訴後に判明したものである。)、問題とすることもできず、ひたすら被告の将来における教師としての大成を期し、貞子を養育しながら婚姻生活の維持に努め、」と挿入する。 四 同22丁表9行目の「みなされたこと」を「噂されていたこと」と改める。 五 同23丁表末行の「その旨を伝え、」を「その旨を伝える手紙を送り、これに」と改める。 六 同25丁裏2行目の「原告を」から3行目の「被告から」までを「原告が赤堀に告げ口をしたとして原告を叱りつける始末であり、また」と、同四行目の「話をもちかけられ」を「話が昭和44年春ころ持ち上がり、」と、同7行目の「作成した。」を「作成したので」と、同9行目の「突き返したため、」を「突き返したこともあつて、原告も」とそれぞれ改める。 七 同26丁表5行目の「割引興業債券100万円券4枚のうち3枚」の次に「(被告は、原告が割引興業債券の他の1枚及び150万円の定期預金証書をも持ち帰つた旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。)」を挿入する。 八 同27丁表2行目の「年収約250万円」を「年収手取り約300万円」と改める。 第二 以上認定の事実によれば、一審原被告間の婚姻関係はすでに破綻し、その回復の見込みがないことは明らかである。そこで、右破綻の原因(責任)につき検討する。 まず、一審原告は、一審被告の不貞行為を主張するが、前記第一引用の原判決理由一(八)の事実は、確かに有婦の夫として好ましからざる行為ではあるけれども、いまだこれをもつて一審被告の不貞を推認することは困難であり、同(九)の女生徒の一審被告による妊娠の噂も、単に噂(特に職員組合からの攻撃材料)だけでは不貞と認めることができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。 一審原被告の間に不和が生じたのは、学園紛争が契機となつて一審被告の学歴詐称、無資格教師(教育職員免許法参照)の事実が一審原告に発覚し、その他一審被告の非違が組合等から指摘され(もつとも、指摘された非違の中には真実であるかどうか疑わしいものもあり、また学院が一審被告に授業をさせていた落度も大きいが、これらの点はさておく。なお、前掲証拠を総合すると、兄小梨朝央も一審被告に反省を求めた事実のあることがうかがわれる。)、ついに一審被告が学院退職を余儀なくされたことから、一審原告としては、一審被告の過去の言動をも思い合わせ、一審被告の人格に対する信頼と将来の婚姻生活への期待を一挙に裏切られたことに原因があると認められる。 もつとも、前記のように一審被告の更生を期して東京で共同生活をするに至つた時点では、一審原告は、父赤堀の説得もあり、一審被告が過去の行為を反省し、破綻に瀕した一審原告との婚姻関係を維持、回復するため、夫としての責任のある生活態度をとるべきことをある程度期待していたと見られるが、その後の一審被告の言動は、一審原告の期待に全く反する不誠実かつ無責任なものであり、前記誓約書の趣旨にもとるようなものであつた(なお、一審被告は国士館大学を卒業したものの、それはずつと後の昭和49年10月である。これは、一審被告本人の原審第1回供述とこれにより成立の認められる乙第15号証で認められる。)ため、特に夫の教師としての大成に自己の生涯をかける一審原告には堪えられなかつたものと考えられる。 ただ、東京での共同生活はわずか9か月程度で終わつており、この点については、実直、潔癖な一審原告において、失意にある一審被告の立場に対する理解と同情が必ずしも十分でなく、一審被告の更生を迫るに急で、最終的には一審原告自身もやや投げやりの気分になつた面もうかがえないではないし、他方、元教育長である一審原告の父赤堀において、一審被告への批判、これに基づく一審原告擁護の姿勢が少々過ぎたのではないかという感も否定できない。 しかし、もとはといえば、人間としての基本的な事柄に関する一審被告の言動が一審原告との婚姻の当初から一貫して誠実さに欠け、それが一審原告の不信を招いたことによるものであり、他方、一審原告にはとりたてていうほどの欠点を認めることはできないから、一審原告が一審被告に絶望したことをもつて、わがままとか期待のし過ぎあるいは単なる性格不一致とか断ずることはできないというべきである。 以上のところを総合すれば、本件婚姻関係の破綻の主な原因(責任)は、一審被告にあるといわざるをえない。とすれば、一審原告が離婚を決意して実家に帰り、別居したことを非難することはできず、したがつてまた、これを一審被告主張の悪意の遺棄と認めることもできない。 第三 一審原告の本訴請求について 一 これまで認定のとおり、一審原被告の婚姻関係が完全に破綻した以上、一審原告の民法770条一項五号に基づく離婚の請求は、理由がある。 二 そこで離婚に伴う子の親権者指定につき検討するに、別居以来母親たる一審原告が貞子、貴子の二児を養育していること、一審原被告双方の生活状態、家庭環境等諸般の事情を総合考慮すると、右二児の親権者を一審原告と定めるのが相当である。 三 次に財産分与の申立につき検討する。 まず一審被告の本案前の抗弁、すなわち一審原告が当審で財産分与の請求を金600万円から金2000万円に拡張したことの適否についてみると、それが財産分与の性質上真の意味の請求の拡張であるかどうかはさておくとして、一審原告は、原審で右金600万円の請求を全部認容されたが、慰藉料の請求の一部が棄却されて適法に控訴し、なお、一審被告からも控訴がされているので、本件全体が当審に移審しており、また控訴審における訴の拡張に別段の制限はないから、控訴の利益けん欠を理由として当審での拡張請求を不適法とする一審被告の主張は、理由がない。 そこで、分与の内容及び額について考えると、一審原被告の共同生活の期間及び状況、資産、収入、資産取得についての寄与、別居後一審原告が持ち帰つた債券の額、別居後の一審原被告及び二児の生活状況とその費用支弁、その他本件に現われた一切の事情を総合考察すれば、一審被告から一審原告に分与されるべき財産は、現金1000万円をもつて相当と認める。 主要な点を摘記すれば、 1 一審被告所有の資産中、前記一関市田村町の土地の持分(2分の1)の昭和50年度の評価額は4300万円以上であるが、その購入資金の大半は一審被告の母良から出ているとはいえ、右不動産は一審原被告が短期間ながら共同生活をした住居地であるし、一審被告が出した一部資金には、一審被告が管理していた一審原告の学院からの給与分(概算171万円)の一部及び一審原告の婚姻生活への寄与分が含まれていると見るのが相当である。 2 一審被告の収入は前記のとおりであるが、一審原告は現在無職で定収及び資産はない。 ただし、父赤堀(現在弁護士で本件訴訟代理人)の仕事を手伝つて給与名義で若干の金員を支給されているほか、教師の資格があるので、将来は定収を得ることは可能であり、その意思もあることが一審原告本人の供述(原審及び当審)並びに弁論の全趣旨により認められる。 3 一審原告本人の供述(当審)及び弁論の全趣旨によれば、一審原告は、別居以来昭和51年まで7年以上にわたり、自己及び二児の生活費、教育関係費として、合計ほぼ1000万円程度を支弁したことが推認される(一審原告主張の右費用算出の根拠である別表記載のうち、消費支出額の算出はおおむね妥当と考えられるが、実費支出を主張する教育関係費中、教養費の内容には、必ずしも必要とは思われない、むしろ生活費に含まれるべきものもあり、また物価指数による補正は認めがたい。これらの事情を勘案し、右金額を認定する。)。 そして、一審被告は右費用を一切負担していない。しかし一方、一審原告が持ち帰つた債券300万円が右費用として費消されたこと、一審原告みずから、別居中の収入として156万円余を主張していること、及び前記支弁費用は大部分父赤堀から出ていると認められるが、それには親子の情誼としてなされた部分もあると考えられること、等を考慮する必要がある。 4 そうすると、分与額は、前記1、2の不動産の清算分及び一審原告の離婚後の生活扶助分として金600万円、3の過去の生活費、教育費の清算相当額として金400万円(かかる費用は婚姻費用であるから、それ自体としては、過去の分についても家庭裁判所が分担を決定すべきであるが、財産分与額決定に際しての事情の一つとして、右費用支弁の清算を考慮に入れることは相当であると解する。)、合計1000万円と認めるのが相当である。 四 さらに慰藉料の請求について検討する。 婚姻が主として一方配偶者の責により破綻し、離婚に至つた場合、他方配偶者は右により被つた精神的苦痛につき、相手方に対し、不法行為による相当な慰藉料を請求することができると解すべきであるが、本件において、婚姻破綻が主として一審被告の責によること、その程度、双方の社会的地位及び収入、年齢、婚姻期間、子の数その他諸般の事情を総合考慮すれば、一審被告は一審原告に対し、金300万円の慰藉料を支払うべきものと認めるのが相当である。その余の慰藉料請求は、理由がない。 第四 一審被告の反訴請求について まず、一審原告に悪意の遺棄が認められないことは前記のとおりであるから、民法770条1項二号に基づく離婚の請求は、理由がない。 次に同条1項五号に基づく離婚の請求についてみると、これまで認定したとおり、一審原被告の婚姻関係が破綻した以上、一審被告にも離婚請求権があるわけである。ただ、有責(主として有責の場合を含む。)配偶者には一般に右請求が許されないとするのが確定した判例であるが、本件の場合、一審原告も離婚を請求している関係上、反訴としての一審被告の離婚請求を同時に認容しても何の幣害もなく、正義に反することにもならないから、結局反訴請求をも認容するのが相当である。 そして、親権者の指定については、本訴において判断したと同断である。 第五 結論 以上のとおりであるから、一審原告の控訴及び請求の拡張に基づき、原判決を変更して一審原告の金員支払の請求中、合計金1300万円の支払を求める部分を認容し、その余を棄却し、一審被告の控訴に基づき、反訴請求についての原判決を取消して右請求を認容し(ただし、親権者指定については、本訴主文と同一であるから、重複掲記しない。)、その余の一審被告の控訴は理由がないから棄却し、本訴、反訴の訴訟費用について民訴法96条、89条、92条を適用し、慰藉料金300万円の支払いを命じた部分につき同法196条を適用して、仮執行の宣言を付し、その余の仮執行の宣言の申立は却下することとして、主文のとおり判決する。 (昭和53年2月27日 東京高等裁判所第七民事部) 別表 以上:7,174文字
|